パソコンを新しく買うとき、「MacとWindows、結局どっちが大学生活に向いてるの?」と悩む人は多いはず。デザインや操作性を重視するならMac、ソフトの互換性やコスパを重視するならWindows…とはいえ、一概には言えないのが正直なところです。
この記事では、大学での実際の使い勝手や専攻別のおすすめポイントなどをもとに、大学生にとってMacとWindowsのどっちがいいかをわかりやすくまとめました。あなたの学生生活にぴったりの一台を見つける参考にしてみてください!
パソコン選びに迷う大学生へ。MacとWindows、それぞれの特徴とは

- デザインや操作性を重視するならMacがおすすめ
- ソフトの互換性と選択肢の多さならWindows
- 値段で比べるとWindowsのほうがリーズナブル
- Macの強み:セキュリティ面での安心感
- Windowsの強み:カスタマイズ性の高さ
- 大学生のライフスタイルに合った選び方を
デザインや操作性を重視するならMacがおすすめ

Macは洗練されたデザインと直感的な操作性で人気があります。見た目にもスタイリッシュで、持ち運んでいても「おしゃれ」と言われることが多いのもMacならではの魅力のひとつです。特にiPhoneやiPadとの連携がスムーズで、写真やメモ、カレンダーの同期も簡単。AirDropやHandoffといった機能を使えば、スマホとパソコン間のデータのやり取りもストレスフリーです。
また、トラックパッドのジェスチャー操作や、Finderでのファイル管理のしやすさなど、細かい部分の使いやすさも秀逸。最初は慣れが必要かもしれませんが、慣れてくるとMac特有の操作性が病みつきになります。デザインや映像、音楽などのクリエイティブな作業とも相性が良く、感覚的に作業を進めたい人には特に向いています。
ソフトの互換性と選択肢の多さならWindows

大学で配布される課題やレポートのテンプレート、授業で利用する専用ソフトの多くは、Windowsを前提に作られていることが非常に多いです。これは日本国内の大学だけでなく、海外の多くの教育機関でも共通している傾向です。そのため、互換性の面では圧倒的にWindowsが有利だと言えます。
特に理系学部や工学部、情報系の学部では、CADソフトや統計処理ソフト、プログラミングの開発環境など、Windows専用のものやWindowsでの動作が最も安定しているソフトを使うことが日常的です。こうした学部ではMacを使うと、仮想環境の構築や代替ソフトの検討といった追加の手間が発生する可能性があります。
また、Windowsにはさまざまなメーカーやモデルのパソコンが揃っており、予算やスペックの好みに応じて機種を選べる自由度の高さもポイントです。軽量なモバイルノートから、性能重視のゲーミングPCまで、多彩な選択肢が揃っているので、自分の学習スタイルや目的にぴったり合う一台が見つかりやすいのも嬉しい点です。
値段で比べるとWindowsのほうがリーズナブル
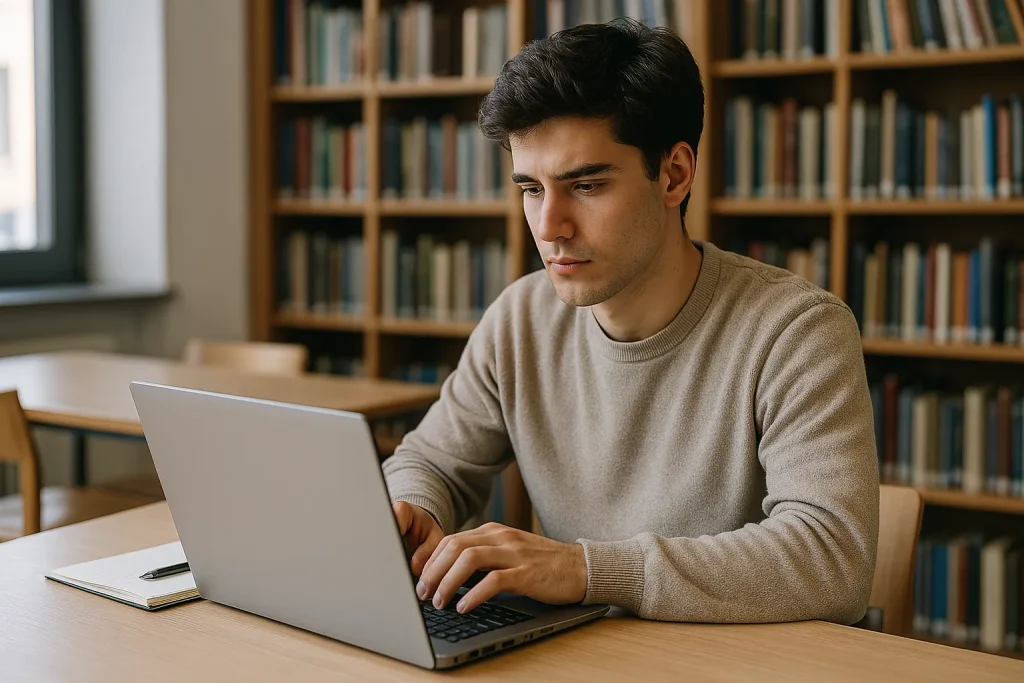
MacはAppleが一貫して高品質・高性能を追求しているため、どうしても価格帯が高めに設定されています。素材やデザイン、製造過程にもこだわっているため、その分コストがかかるのです。特に学生にとっては、初期費用が高く感じられることも多く、「ちょっと手が届きにくい」と感じる人も少なくありません。
一方のWindowsは、さまざまなメーカーが製造しているため、価格帯のバリエーションが非常に豊富です。3万円台のエントリーモデルから、20万円を超えるハイエンド機種まで幅広く取り揃えられており、自分の予算や使用目的に応じたパソコンを見つけやすいのが特徴です。
また、セールや学割、キャンペーンを活用すればさらにお得に購入できることも多く、コストパフォーマンスを重視する大学生にとっては大きな魅力となります。入学時や新生活シーズンには、量販店やオンラインショップで特別価格になっていることもあるため、タイミングを見て賢く選ぶのもひとつの手です。
Macの強み:セキュリティ面での安心感
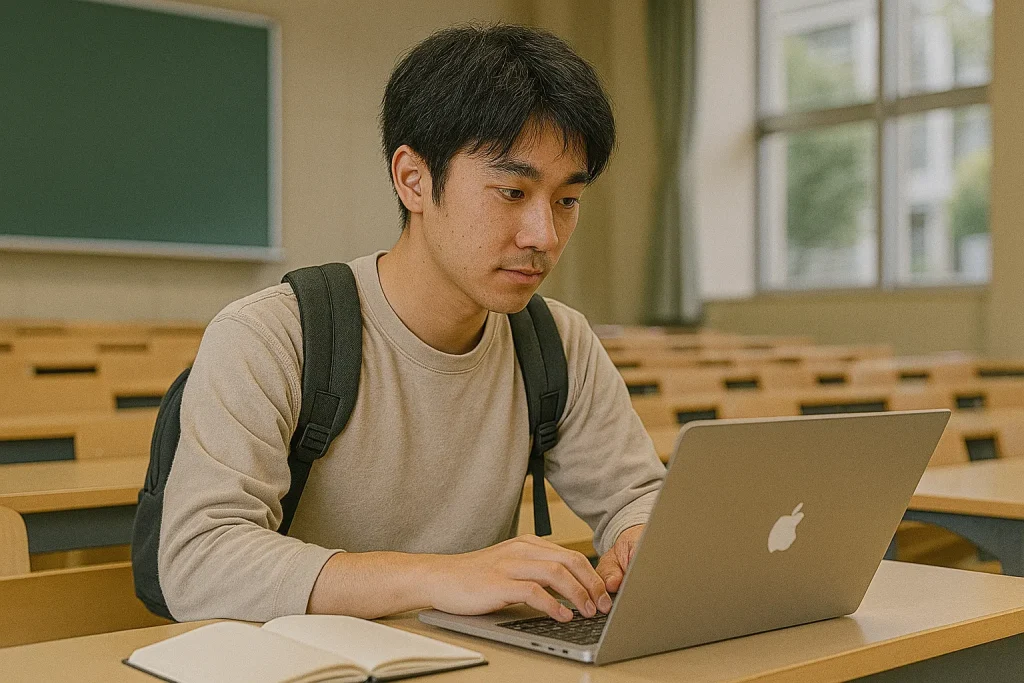
Macはウイルスに強いと言われており、セキュリティ面を重視する人にとっては非常に魅力的な選択肢です。Appleは独自のOSであるmacOSを採用しており、Windowsと比べてウイルスやマルウェアの標的になりにくい構造となっています。これは市場シェアの違いもありますが、Appleがシステムやアプリの管理を厳格に行っていることも一因です。
また、初期状態からGatekeeperやXProtectといったセキュリティ機能が標準搭載されており、不審なアプリのインストールや実行を防いでくれます。さらに、Safariブラウザにも追跡防止機能があり、ネットの利用時にもプライバシーを守ってくれる設計になっています。
セキュリティソフトをわざわざ購入しなくても、ある程度の保護が最初から備わっているため、パソコン初心者やセキュリティにあまり詳しくない人でも安心して使うことができます。もちろん完全に安全というわけではありませんが、トラブルのリスクを少しでも下げたい大学生には心強いポイントになるでしょう。
Windowsの強み:カスタマイズ性の高さ
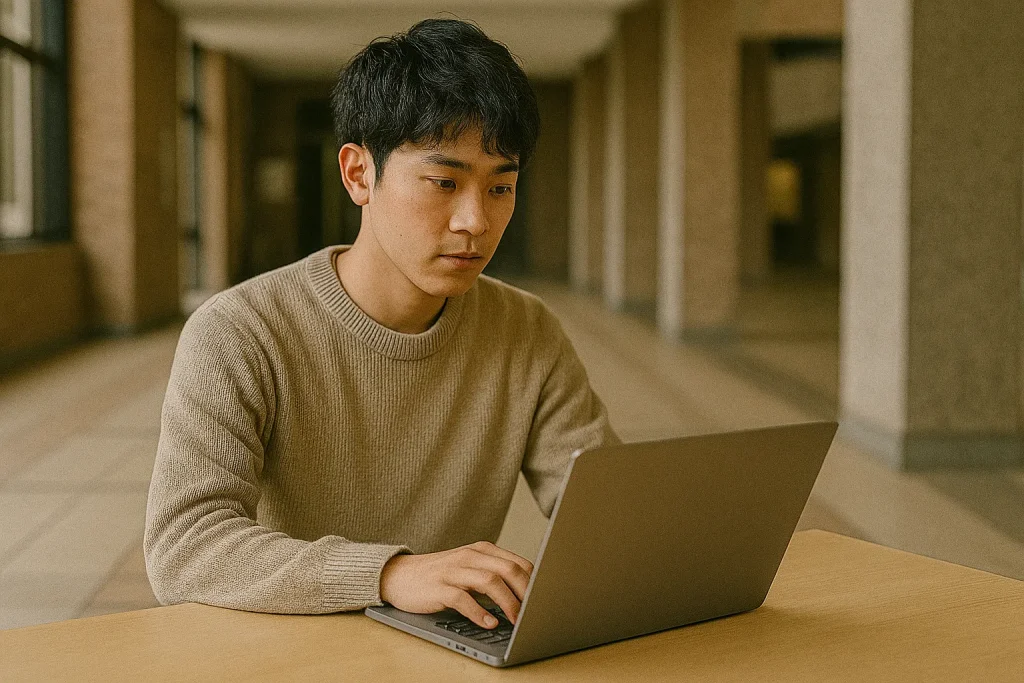
WindowsはPCのカスタマイズがしやすく、自分好みにハードやソフトを変更できるのが大きなメリットです。特に自作PCやパーツの交換に興味がある学生にとっては、自由度の高いプラットフォームとして非常に魅力的です。たとえば、メモリの増設やストレージの交換、グラフィックボードの追加などが比較的簡単に行え、自分だけの最適な環境を構築できます。
また、ソフトウェア面でも多様な選択肢があり、さまざまなアプリケーションを導入できる点も強みです。オープンソースのソフトから高度な専門ツールまで幅広く対応しており、自分の学習スタイルや趣味に合わせてカスタマイズすることが可能です。加えて、Windowsはゲームにも強く、多くのゲームがWindows向けに最適化されているため、勉強の合間にゲームを楽しみたいという学生にも適しています。
このように、カスタマイズ性の高さは単にパーツ交換やソフトのインストールにとどまらず、自分のライフスタイルや学習スタイルに合わせた環境を作り上げられるという点で、非常に大きな利点になります。
大学生のライフスタイルに合った選び方を

文系・理系といった専攻の違いに加えて、日常的にどのような用途でパソコンを使うかによって、適したモデルは大きく変わってきます。たとえば、文系学生なら主にレポート作成や資料閲覧が中心となることが多く、軽量で持ち運びしやすいモデルが重宝されます。一方、理系学生や情報系の学部では、プログラミング、データ解析、実験レポート作成など、より処理性能が求められる場面も多くなるため、スペック重視の選択が必要になるでしょう。
また、動画編集やグラフィックデザインなどを行う学生には、クリエイティブ系ソフトとの相性も重要です。Macはその点で優れており、iMovieやFinal Cut Pro、Adobe製品との連携もスムーズです。さらに、通学時のスタイルによっても選び方は変わります。毎日ノートパソコンを持ち歩く必要がある人は、軽さやバッテリー持ちの良さを重視した方が快適です。逆に自宅中心で使うなら、多少重くても性能重視のPCを選ぶのもアリです。
このように、自分の学部や生活スタイル、使いたいアプリケーションを具体的にイメージしながら選ぶことで、パソコン購入の失敗を防ぐことができます。なんとなくで選ぶのではなく、実際の使用シーンを想定して比較するのが、納得できる選び方への第一歩です。
実際の大学生活で感じたMacとWindows、それぞれの使い勝手

授業で使うならどっちが便利?

PowerPointやWord、Excelなど、授業で使われる定番のオフィス系ソフトに関しては、MacでもWindowsでもほぼ問題なく使うことができます。Microsoft 365(旧Office)も両OSに対応しており、基本的なレポート作成やプレゼン資料の作成には不自由しません。
ただし、細かい機能やショートカットキーの配置がOSによって異なるため、最初のうちは戸惑うこともあるかもしれません。特にMacでは「control」や「command」など、Windowsとは違ったキー操作が必要になるため、使い慣れるまでに少し時間がかかる人もいます。
また、一部の大学や特定の講義では、Windows専用の教育用ソフトが使われる場合があります。たとえば、経済学部の統計ソフトや工学部でのシミュレーションツールなどがそれに該当します。そうした場合、Macではそのソフトが動作しないか、仮想環境を構築しないと利用できないケースも出てくるため、事前に大学の授業内容やシラバスを確認しておくことがとても重要です。
総じて、基本的な授業であればどちらでも対応可能ですが、専用ソフトが必要な学部や授業ではWindowsの方がトラブルが少なくスムーズに進められる傾向があります。
レポートや論文作成での違い

文章作成自体に関しては、MacでもWindowsでも特に問題はなく、WordやGoogleドキュメントなどの主要な文書作成ツールはどちらの環境でも快適に使用できます。ただし、文書作成に加えて参考文献の管理や自動引用、脚注機能などを駆使して本格的にレポートや論文を仕上げる場合、Windowsの方が対応しているツールが多く、スムーズに作業が進むケースが多いです。
たとえば、研究者や大学院生にもよく使われる文献管理ソフト「EndNote」や「Mendeley」、「Zotero」といったツールは、Macでも動作しますが、Windowsでのほうが安定していたり、Wordとの連携機能が強力だったりすることがあります。また、大学によっては独自のテンプレートや提出フォーマットがWindows向けに最適化されていることもあり、そのままMacで使うとレイアウトが崩れてしまうといった事例も見られます。
一方で、Macでは「Pages」などApple独自のワープロソフトを活用することも可能ですが、これらは提出先との互換性や変換の手間を考慮すると、やや不便に感じる場面もあるかもしれません。加えて、一部の論文投稿用フォーマットや提出システムがWindows専用だったり、Windows上での操作を前提に作られていることもあるため、文系・理系問わず、自分の学部や研究テーマに合った環境が整っているか事前に確認しておくことが大切です。
動画編集やデザイン制作ならMacが人気

YouTuberや映像・音楽系の分野、デザイン系の学部において特に人気なのがMacです。Appleが提供するクリエイティブツールは、操作性や処理速度に優れ、初心者でも直感的に扱いやすいのが特徴です。中でもFinal Cut ProやLogic Proは、プロ仕様でありながらユーザーフレンドリーな設計で、映像編集や音楽制作を行う学生にとって強力な味方となります。
さらに、Adobe製品との相性も良く、PhotoshopやIllustrator、Premiere Proなども快適に動作します。高精細なRetinaディスプレイを備えている点も、デザインや動画編集において色味や細部を確認しやすく、作品のクオリティアップにつながります。また、トラックパッドの感度が非常に高く、細かな編集作業をストレスなく行えるのもMacの大きな利点です。
作業中の動作の安定性やバッテリー持ちの良さも、外で作業するクリエイター系の学生には嬉しいポイント。軽量なMacBook Airや、パワフルなMacBook Proなど、用途に応じて選べるモデルもそろっており、デザイン・映像・音楽など、クリエイティブな活動を主軸にする大学生にはMacが非常に人気です。
プログラミングを学ぶならどっち?

プログラミングに興味がある大学生にとって、どちらのパソコンを選ぶかは非常に重要なポイントです。まず、文系の学生やプログラミングをこれから始めたいと考えている人にとっては、Macは非常に扱いやすい選択肢です。Macはターミナル操作に強く、UNIXベースの環境が整っているため、PythonやRuby、JavaScriptなどの言語を学ぶ際には非常に便利です。
特にiOSアプリの開発を考えている場合、Appleが提供する「Xcode」という開発ツールはMac専用であり、iPhoneやiPad向けのアプリを開発するにはMacが必須となります。そのため、iOSアプリに興味がある場合は迷わずMacを選ぶべきでしょう。
一方で、WindowsはWindows向けのアプリケーション開発や、ゲーム開発、C#や.NETを使った開発において非常に強みがあります。また、多くの統合開発環境(IDE)がWindowsでの使用に最適化されていることもあり、Visual Studioを活用するプログラミング学習にはWindowsが圧倒的に使いやすいです。
加えて、情報系学部ではLinux環境が必要になることもありますが、その場合、Macでは比較的スムーズに仮想環境やターミナル操作を行える一方、WindowsではWSL(Windows Subsystem for Linux)を利用することでLinuxの操作にも対応できます。
最終的には、学びたい言語や将来目指す分野、使いたい開発ツールによって適したOSが異なってくるため、自分の方向性をある程度イメージしておくことが大切です。
持ち運びやすさで見ると?

軽さやバッテリーの持ちで見ると、MacBook Airはかなり優秀なモデルです。重量は1.3kg前後と非常に軽く、バックパックに入れて持ち運んでも負担になりにくいのが魅力です。また、バッテリー持ちも最大18時間と長く、1日中大学で使っても電源を探す必要がないという安心感があります。
一方で、Windowsにも軽量なモバイルノートは数多く存在し、PanasonicのLet’s noteシリーズや富士通のLIFEBOOKシリーズなどは1kg未満の超軽量モデルも登場しています。これらは電車通学や講義の移動が多い学生にとって非常に頼もしい相棒となるでしょう。
また、ノートパソコンのサイズ選びも重要なポイントです。13インチ前後のモデルは画面の見やすさと携帯性のバランスが良く、カフェや図書館での作業にも適しています。最近では14インチでもベゼルが狭く、本体サイズがコンパクトなモデルも増えてきており、選択肢が広がっています。
結局のところ、持ち運びやすさは単に軽さだけでなく、バッテリーの持ち、サイズ感、耐久性といった複数の要素で判断する必要があります。通学頻度やキャンパス内での移動スタイルに応じて、自分にぴったりの一台を選ぶのがポイントです。
周囲の学生の傾向は?

文系はMac派、理系はWindows派が多いという傾向は、実際に多くの大学で見られる現象です。特に文学部や教育学部、経済学部などの文系学部では、MacBookを使っている学生を多く見かけます。Macは軽量でスタイリッシュなデザインが魅力的なため、持ち運びやすさや見た目を重視する学生に支持されているようです。また、iPhoneやiPadとの連携も便利なので、すでにApple製品を使っている学生にとってはMacを選ぶ自然な流れとなっていることも。
一方、理系学部、特に工学部、情報系、理学部などではWindowsユーザーが圧倒的に多いです。これは、大学で使う専用ソフトの多くがWindows向けであったり、Windowsのほうがスペックの自由度やカスタマイズ性が高く、研究や開発などの用途に適しているためです。また、学部によっては教授が指定するソフトやツールがWindows専用ということもあり、最初からWindowsを選ばざるを得ないケースもあるようです。
実際に大学の教室を見渡すと、デザイン系の学部ではMacユーザーが目立ち、教室に並ぶPCがほとんどAppleロゴという場面もしばしば。一方で、工学系の講義では多種多様なWindows機が並び、ガジェット好きや自作PCに詳しい学生も多く見られます。このように、学部や学科ごとの特性や学びのスタイルによって、使われているパソコンの傾向がはっきり分かれているのが実情です。
まとめ:大学生にとってMacとWindows、どっちが使いやすい?
- デザイン・操作性重視ならMac
- スタイリッシュな見た目、Apple製品との連携が快適
- 直感的でシンプルな操作感が特徴
- 互換性・選択肢の多さはWindows
- 大学指定のソフトや課題に対応しやすい
- メーカー・モデルが豊富で自分に合ったPCを選びやすい
- 価格重視ならWindows
- 幅広い価格帯から選べてコスパ◎
- 学割やキャンペーンでさらにお得に買える
- セキュリティ重視ならMac
- 初期状態から高い安全性が確保されている
- ウイルス対策に詳しくない人にも安心
- カスタマイズ重視ならWindows
- パーツ交換やソフト導入の自由度が高い
- ゲームや専門用途にも対応しやすい
- 専攻・使用目的に応じて選ぼう
- 文系(レポート・持ち運び)ならMacも◎
- 理系(ソフト重視・開発用途)ならWindowsが堅実
- 授業・レポートはどちらでもOKだが…
- 一部ソフトはWindows専用のため要確認
- 文献管理ツールなどの連携面ではWindowsが有利な場合も
- クリエイティブ作業ならMacが強い
- 動画・音楽・デザイン系の作業に最適
- プログラミングは目的別に選ぶのが正解
- iOSアプリ開発 → Mac
- ゲーム・業務アプリ → Windows
- 持ち運び重視ならどちらも対応可能
- MacBook Airや軽量Windowsモデルは通学に最適
- 周囲の学生の傾向を参考にするのもアリ
- 文系:Macが多め/理系:Windowsが主流

